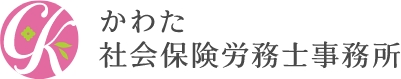障害年金がもらえない人へ|不支給の原因と再請求または審査請求で受給するための完全ガイド
障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に制限が生じた場合、生活を支える大切な社会保障制度です。
しかし、実際には請求者の約3割が「不支給通知」を受け取っている現実があります。
「なぜ自分は障害年金をもらえないのか」「再請求すれば受給できるのか」と悩む方は少なくありません。
本記事では、障害年金がもらえない主な原因と、再請求または審査請求で受給を目指すための具体的な戦略を、最新の制度情報や実例を交えて徹底解説します。
あなたが諦めず、適切な手順で再チャレンジできるよう、わかりやすくガイドします。
1. 障害年金が不支給となる主な原因
ご相談をいただいた中で、不支給になる理由の多くは次の3つです。
1-1 障害の状態が軽い
障害年金は、障害の程度が「認定基準」を満たしている必要があります。
・診断書の記載が不十分
・日常生活や就労への影響が具体的に書かれていない
・精神疾患の場合、主観的な症状のみで客観的制限の記載がない
対策:
・医師に「日常生活でどのような支障があるか」を具体的に説明し、診断書に反映してもらう
・家族や職場の方から、困っていることやサポート状況等を添付する。
1-2. 初診日証明の不備
障害年金の請求では「初診日」が非常に重要です。初診日が証明できないと、請求自体が認められません。
よくあるケース:
・何年も前の受診でカルテが廃棄されている
・病院が廃院している
・転院を繰り返し、初診日がどこかわからなくなった
対策:
初診日の特定できる資料がみつからない場合は、社会保険労務士にご相談ください。カルテの写しや領収書、健康診断の記録の写しなどをつけて初診日を証明できる場合があります。
請求した初診日より前に、因果関係がある症状で病院を受診していた場合は、初診日を前にずらして再請求することもできます。
1-3 保険料納付要件の未達 保険料納付要件を満たしていない
障害年金の受給には、「(*1)保険料納付要件」を満たしていることが絶対条件です。
初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの
・直近 1 年間の保険料の未納がないこと
または
・被保険者期間で、納付済期間と免除期間を合わせた期間が 3 分の 2 以上あることです。
よくあるケース:
・学生時代や無職期間の未納が多い。
・免除申請をしていなかったため、未納期間になっている。
・国民年金第 3 号被保険者(配偶者の扶養)期間の届け出もれ
注)初診日を過ぎてから追納や免除の申請をしても保険料納付要件は満たせません。
※ただし、社会的治癒が認められ、初診日が変わった時点で保険料納付要件を満たしていれば再請求できます。
2. 見落とされやすい対象疾患
発達障害や難病、精神疾患などは「等級非該当」とされやすいですが、日常生活や社会適応の具体的制限を丁寧に立証すれば認定される事例も多くあります。
3. 不支給通知を受け取ったらやるべきこと
3-1. 不支給理由の確認
まずは「不支給通知」に記載された理由を正確に把握しましょう。
3-2. 不支給になってしまった後の手続き
〇 不服申し立て(審査請求、再審査請求)
不服申し立ては、最初に提出した書類関係を基に審査されます。
そのため、不支給になった理由に対して受診状況等証明書、診断書、病歴就労状況等申立書の内容が支給の基準を満たしていることを証明していくことになります。
提出した診断書の実際の症状よりも軽く書かれていたとしても、根拠なくそのことを審査請求の理由として主張しても認められません。結果を覆すには客観的根拠をもとに障害年金の受給要件を満たすことを主張しなければなりません。
〇 再請求(もう一度最初から手続きをやり直す方法)
障害年金は一度不支給になっても、何度でも請求は可能です。
再請求する場合は、再度、診断書、病歴就労状況等申立書等の書類を整備して日本年金機構に提出します。
しかし、提出した診断書、病歴就労状況等申立書等の提出した書類はすべて日本年金機構で保管されており、新たに提出する書類等との整合性が取れなければ障害年金の支給決定はされません。
再請求する場合は、『以前に提出した書類関係を精査し、整合性の取れない箇所はないか』や『前回提出した時に、内容的な不備がないか』を確認して提出する必要があります。再請求をするには、初めて請求するよりハードルが高くなります。
ちなみに前回提出した請求書類一式の写しは、年金事務所から郵送してもらうことができます。
3-3. 不服申し立て期限
・審査請求は不支給通知を受け取ったら、3 ヶ月以内に行う必要があります
・再審査請求は決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して 2 か月以内に行う必要があります。
審査請求より期限が 1 か月短いので注意しましょう。
3-4 専門家の活用
障害年金は1度請求してしまうと年金機構に記録が残るので、2回目以降の請求で認定を受けることが難しくなります。
社会保険労務士(社労士)は障害年金の請求に精通しており、書類作成やアドバイスを受けることで成功率が大幅に上がります。
病院等への対応も可能です。無料相談もやっているので気軽に相談してください。
4. 再請求成功事例
ここから再請求成功事例をご紹介いたします。
事例 1:統合失調症で再請求が成功したケース
・1回目の請求では、診断書に幻聴や妄想などの具体的な症状が記載されていなかったため不支給となった。
・家族が日常生活での困難さを詳細に記録し、その内容をもとに医師へ再度説明してもらった結果、2回目の請求で受給が決定した。
事例 2:難聴による障害年金の再請求が受理されたケース
・初診日が40年以上前でカルテが残っていなかったが、職場の健康診断記録やお薬手帳などの補足資料を提出。
・社会保険労務士の助言を受けて必要書類を揃え、障害年金の再請求を行い受給が決定。
事例 3:発達障害で等級非該当から認定へ逆転したケース
・日常生活の支障を具体的に記載した診断書に書き換え、専門家のアドバイスで再請求。
・就労支援事業所の職員からの証言も添付し、認定に至った。
5.よくある質問(FAQ)
Q1. 働いていても障害年金はもらえますか?
A. 一定の就労や収入があっても、障害の程度が基準を満たせば受給可能です。就労の有無だけで判
断されません。
Q2. 生活保護と障害年金は併用できますか?
A. 併用可能ですが、障害年金を受給すると生活保護費が減額される場合があります。
Q3. 診断書はどのように書いてもらえばいいですか?
A. 日常生活や仕事での具体的な制限や困難を、できるだけ詳細に記載してもらうことが重要です。
6.まとめ
障害年金の不支給通知を受け取っても、諦める必要はありません。
・保険料納付要件・初診日証明・診断書内容を見直し、
・必要に応じて専門家の力を借りて、
・再請求や不服申し立てを行うことで、受給できる可能性は十分にあります。
特に、診断書の「具体的な日常生活の制限」の記載や、初診日証明は、再請求成功のカギです。
自分ひとりで悩まず、家族や専門家と連携して行動しましょう。
障害年金の請求は、知識と十分な準備があれば成功率が大きく変わります。
本記事を参考に、ぜひ一歩を踏み出してください。